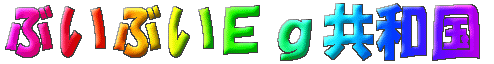●2015年06月04日(木)

久々の、クルマネタです〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜@
そもそもあんまりクルマに乗らないので、ネタになるコトはそんなにありません。
でも先月は、何回目かの「車検」だったのです。
当然ながらユーザー車検で通して来ましたが、特に問題もなくスムーズに通る・・・・・ハズでした。
しかし、アクシデントは「スピードメーター試験」の時に発生!
スピードメーターの試験は、ローラー上にクルマを乗せて、ギヤ入れてアクセル踏んで40km/hまで自分で加速いたします。
そして40km/hになった時点で、昔はリモコンスイッチを押してたんだけど、現在では「パッシング」で合図するコトになっております。
実は、そのパッシング動作が不調。(ようするにパッシングにならない、点灯しない)
???とアタフタしている間にタイムオーバーになってしまいました。
ユーザー車検に行く前には、必ず灯火類のチェックを行います。
ヘッドライトH/Lの点灯、ウインカーにハザード、車幅灯、ストップランプにナンバー灯にバックランプ。
その他にもワイパー&ウォッシャー作動なんかも見ておきますねぇ。
これらはいくら常時整備してあっても、運悪く切れていたりするコトがあるんです。
そもそも自分の運転している間はこれらのランプの点灯具合なんか基本的に見れませんから、もし切れていても気がつかないコトだってあるのです。
でも、パッシングの動作に関しては盲点でした・・・・・。
確かに直接テストする項目はありませんが、スピードメーター試験時に使いますからねぇ。
あーバカバカバカ〜、と自己嫌悪。
そう言えばちょっと前に、確かにこのパッシング動作が調子悪いコトを確認してはいたのです。
接触不良なのか、時々しかつかないんですよねぇ。
まぁ古いから仕方ないかと思って、ソレっきり忘れてました。
と、ここまで走馬灯のように思い出しました。
でもスピードメーター試験やヘッドライト試験の場合、2回チャンスがあるのです。
だったらラストチャンスに全てを掛ける!と言う事で気を取り直して、リトライ。
(ちなみにテスター上に載ったままでやり直しですよん)
今度はちょっとインチキだけど、ヘッドライトスイッチをonしてハイビーム点灯、そして消す動作にてしのぎました。
MT車でこんな操作をするのは苦労しましたが、何とかクリヤー。
他の項目も全てクリヤーして、合格しました。
あー疲れた。
んで、そのままの状態ではいけませんから、パッシング機能の修理をいたします。
パッシングは純粋に、ヘッドライトスイッチ回路の接点でやってます。
通常のヘッドライト点灯はHi/Low共に正常ですから、まずスイッチ自身の不良でしょうねぇ。
ここで勘違いされると困りますので、働くカウンタックことホンダ・アクティトラック(HA3)のライトスイッチ操作に付いて説明します。
スモール/ヘッドライト点灯はハンドル右側のレバーにて行います。
レバー先端のツマミをヒネると、消灯>スモール点灯>ヘッドライト点灯となります。
これは普通のクルマと同じですねぇ。
ちなみにレバーの上下はウインカーでして、これまた普通のクルマと一緒です。
そしてヘッドライトのHi/Lowの切り替えなんだけど、これはレバーを手前に引いて行います。
通常はLow点灯として、一回レバーを引くとHiに切り替わります。
そしてもう一度レバーを引くと今度はLowに切り替わります。
つまり、レバーを手前に引く度に、HiとLowとが交互に切り替わるようになっているのです。
これは多分、このホンダのクルマ特有の操作法じゃないかなと思いますねぇ。(他にホンダ車に乗ってないので判りません)
そして問題のパッシングは、レバーを途中まで微妙に引くと、バッシングになるんです。
最後まで引ききらなければ元の点灯状態へ復帰するって寸法です。
(もし最初に消灯していれば消えている状態になる)
普通のクルマだと、レバーを向こう側へ倒すとその位置に固定されてHi側が点灯。
レバーを手前に戻すとLow側が点灯。
そしてパッシングはレバーを手前に引くと、引いている間だけパッシングになるってのが一般的でしょうねぇ。
つまり、私の運転時の気性が荒くてパッシングばかりしていて接点が磨耗したワケではないんです。
自然に、ヘッドライトのHi/Lowを切り替える度にパッシングの位置を使うんですから。
そして田舎に住んでいる私は、ヘッドライトのHi側もしょっちゅう使うんです。
ライトスイッチは、ちょっと迷ったけれど中古品で済ませました。
消耗する部分なので本来なら新しい部品が良いんですが、\1,000-とすごく安かったので。
早速、交換作業です。
実はこの部分はバラした事がありませんので、初めて触るのでチョッピリ緊張感がありますねぇ。
ステアリングコラムに付いているので、まずはステアリングコラムカバーを取り外します。
すると、目的のライトスイッチがモロ見えになります。
手元の良品と比べると、どうやら固定は小さなネジ2本のみで、枠に嵌め込みになっているようですねぇ。
操作する力がある程度掛かる割りに、華奢な固定方法です。
かろうじてドライバーも入りますから、もしかして楽勝モード突入?と一瞬思いました。
でも残念ながら、ホーンスイッチ回路の接点とかがあるので、やっぱりズルをせずにステアリングホイールを取り外した方が良さそうですねぇ。
エアバッグもオーディオスイッチも何も付いていませんから、ナット1本だけで取り外せるのです。
でも、このステアリングホイールの取り付けには散々苦労させられました。
と言うのも、なかなか上手くセンターが出せなかったんですねぇ。
車体が直線状態なのにハンドルが微妙に切れているんです。
これがすごく気持ち悪いので、しっかりセンターに合うようにステアリングボスの向きを変化させたり試行錯誤して、ようやく現在のように落ち着いたんですねぇ。
なので、ステアリングホイールとステアリングボスは、もう二度と外したくないと思っとります。
もし取り外し作業をする必要が出てきたら、ちゃんと目印をしておいて元通りに出来るようにするでしょうな。
ちなみにステアリングナットは対辺19mmですから、タイヤ交換用のクロスレンチでokでした。
ステアリングホイールをボス毎取り外すと、取り付け部分は随分と汚れてますねぇ。
これはボス部分の、ホーン回路接点が削られたカスなのです。
ここまで分解すると、ほぼ剥き出しなのでスイッチ交換がスムーズに出来ます。
急がば回れってヤツですねぇ。
スイッチを良品と入れ替えて、付いていた様に元通りに組み立てて完了。
そして念入りに、各スイッチ機能の動作チェックを行います。
と、ここでまたアクシデント発生!
何とウインカーが左右どちらも点灯しません。作動しません。
やべー、コネクタの刺し方が甘かったかなと、一端ステアリングコラムカバーを取り外してチェックしました。
でも、コネクタ部分には異常はありません。
ここでふと気が付きました。
このクルマはハザードのスイッチがステアリングコラムの上に付いてて、右側へスライドするとハザードONになります。
どんなクルマでもですが、ハザードのモードに入るとウインカー動作は一時的にキャンセルされてハザード優先となるんですねぇ。
つまり、原因はハザードのスイッチが完全に左側のoffポジションになく、微妙に中間位置だった所にあります。
こうするとウインカー回路はキャンセルされるので、ウインカーが出なくなっちゃうんですねぇ。
でもハザード作動する所までスイッチが動いていないので、当然ハザードは出ていないんです。
つまり、ステアリングコラムカバーの脱着時にハザードスイッチにちょっと当たって、スイッチの位置が微妙な所にズレてしまっただけなのでした。
でも、これって実際の運転中にも起こり得るトラブルですよねぇ。
もしも突然ウインカーが出なくなったら、とても危険な状態になると思うのです。
まぁ最近のクルマはハザードスイッチは大抵がプッシュ式のオルタネート動作するスイッチになってますけど。
てなワケでして、ダブルパンチのトラブルはあったけれど、無事に「働く★カウンタック」は修理完了しました。
ちなみに去年行った、エアコンのガスチャージは有効だったようでして、今現在もエアコンの効きはとても良好です。
でもなんかカーステレオが最近おかしいような気もしますねぇ。
音量が小さくなったような気がするし、ずーっと使っていたUSBメモリが認識できなくなっちゃったし。
そのうち、もしかしたらここら辺の顛末がコラムネタになるかも知れません。
|