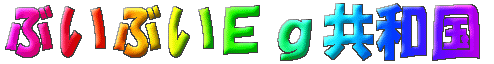●2011年05月21日(土)

本日は、PCと言うか家電というか、オーディオっぽいモノのお話です。
私が愛用している音響関連の機器で、「あったら便利」といつも思うのがこのヘッドホンアンプです。
(以下、HPアンプと省略します)
オーディオテクニカの製品でして、品番はAT−HA2。
詳細は、★メーカーのサイトへのリンク★をどうぞ。
希望小売価格が\7,000-で、ネット通販とかで調べると実売価格が\6,000-前後ってのがほとんどです。
中古品はこれよりかは安いけれど、元々のお値段がこんなものですから、よほど安く買わないとメリットは無いような。
某ハー▲゛オ■に、「中古品:\5,000-」とのびっくりプライスが付いていた事件もありましたけどね。
スペックはさておいて、機能は下の通りです。

オーディオ入力はステレオで、RCAピンとミニジャックの2系統あります。
でもこれは内部で繋がっていて、丁度オーディオ再生機器とアンプの中間に入れて使えるようにもなってます。
もちろんですが、本体の電源が入っていなくても繋がってるんです。
もしも、このアンプが最終段ならば片側の端子だけ使えばokですよん。
出力は、ステレオミニジャックが2本あり、同時使用が可能です。
各系統にon/offの切り替え機能とかがあればより便利ですが、シンプルさが売りなので仕方ないですね。
特徴的なのが、電源ユニットです。
いわゆるACアダプタなんですが、その電圧がDC15vとかな〜り「増幅回路の都合」的なんですねぇ。
私は、富士通のノートPC用のACアダプタを使っています。
高性能なスイッチング電源ユニットですので、音質的にも有利になるかと。
もっともアンプ内部を解剖して見ると判るんですが、本体内で12vレギュレター通してるんですけどね。
外観からの予想通り、中身はICアンプ一発のシンプルな回路構成です。
JRC(新日本無線)製の、NJM2073と言うパワーアンプICですねぇ。
ここで気を付けなければならないのは、「オペアンプ」ではなく「パワーアンプ」なんです。
つまりこのICだけで小型のスピーカを直接くっ付けて鳴らすコトが出来るんですな。
電源電圧が、1.8v〜15vととても幅広いのも特徴です。
汎用性が高くて、あちこちで良く見かけるのも頷けます。
一応、このHPアンプの評価やインプレとかをネットで調べてみました。
すると・・・「ノイズが多い」と言う意見が実に目立ちます。
どうやら、ネット特有の、悪評レッテル貼りをされちゃったみたいですねぇ。
現物がここにありますんで私は検証が出来るのですが、このHPアンプ自体のノイズなんて全然大したコトはありません。
実はアンプってのにはどうしてもノイズは付き物なんだけれど、その発生源は外部機器との組み合わせから来ているケースが殆どです。
それと、ヘッドホンの仕様に関しても重要だったりします。
相性があるんですよねぇ。
ポータブル機器での使用も想定したヘッドホンは、効率が良くて「鳴りやすい」設計となってます。
でも一昔前の音響製品としてのヘッドホンだと、充分なパワーを持つアンプで使う前提になってる「鳴りにくい」のが殆どです。
これは使い道の問題ですから、良いとか悪いとかの話ではありません。
そしてHPアンプってのはどちらかと言うと「鳴りにくい」タイプのヘッドホンを使う前提に設計してあるのです。
もちろんですが低インピーダンスのヘッドホンを繋いでも大丈夫なようになってはいますけどね。
普通に使う分には、そんなヘッドホンの仕様なんてのをいちいち意識する必要はありません。
このHPアンプだってメーカーが推奨するヘッドホンはこれですなんて言っていませんし。
でも、HPアンプは性能や特性が、ヘッドホンとの組み合わせにより大きく変わってしまうんです。
それを踏まえずに、アレコレと製品を評論しても無意味なんですよねぇ。
で、HPアンプの実際に使う状態でのインプレです。
組み合わせる機器によっては、とてもノイズが目立って聴きづらくなる場合があります。
ポータブルオーディオ機器やPCの音声出力との接続では、ノイズがかなり大きくなってしまいますねぇ。
ヘッドホン事態の効率が良いと、より顕著です。
・・・なんて書いてますけど、そもそもナンセンスなんですよねぇ。
元々の再生機器でノイズだらけなのに、そこにアンプ繋いで増幅すりゃノイズが大きくなって当然なんですから。
こんな基本的なコトを忘れて、「AT-HA2はノイズだらけ」なんてしたり顔で公言してんですから、毎度恐れ入ります。
まぁせいぜい「場合によってはノイズの影響を受けやすいかも知れない」程度にしておげば良いのに。
アンプICに関して調べても、やはり同様のレッテル貼りがありました。
こういう部品ってのは、部品単体での性能の優劣を語る前に、まずどんな仕様のモノを求めるのかってのが大事なんです。
汎用パワーアンプのICをつかまえて、オペアンプICの基準での考えでアレコレ酷評するのは間違っていませんかねぇ。
例えて言うと、日本料理の真髄を極めようって人物が、激辛のカレーライス喰って評論してるようなモノです。
総括して言いますと、このHPアンプは「ごく普通に音量が欲しい場合に使う」という明確な目的で、シンプルに設計された製品です。
特筆すべき点は・・・・これと言ってありませんねぇ。
そもそも部品点数からして少ないんですから。
とは言いつつも、揚げ足をとったり無い物ねだりしたりするのがオーディオマニアの悲しい性質です。
なので改造ネタが、実に沢山出てきてますねぇ。
無難なのが、使っている部品のグレード自体を上げる方法。
コンデンサーなんかは一般用のモノを使ってますけど、これを定数をイジらずにオーディオ用とかの高級品に交換するんです。
たしかにこれは良い方法ですねぇ。
使っている部品点数は知れていますので、費用だってそんなに掛かんないですし。
もう一つは、定数変更。
そもそもICアンプってのは、外付け部品の定数によって動作点を決めて使ってます。
なので、それをいじってあげれば仕様特性を大きく変えることが可能です。
もちろんですが・・・・設計の都合でその定数は決まるので、むやみやたらにイジるのは良くないですよ。
ちょっと小手先で音が良くなったりするんなら、そもそもメーカーの設計者がやってますから。
「自分以外は皆馬鹿」みたいな尊大な考えをお持ちの方はやたら変えたがりますけどね。
よくやる手法は、増幅率を抑制してノイズを減らすんです。
もちろん音量もそれにつれて小さくなりますけど、ボリューム位置に余裕があれば問題とはなりませんし。
あと出力ラインへ直列に抵抗器を入れる(又は抵抗値を増やす)方法。
インピーダンスを高くしてあげると、アンプの特性が変わって「良くなった」と思い込みやすかったりもします。
使っているヘッドホンが効率の良い「鳴らせ易い」タイプならばある程度有効な方法です。
これが紹介されているコトが昔から多いですねぇ。
そもそも、HPアンプの使い道ってのはどんなのでしょうか。
PC用に使う場合、音声の出力レベルが小さくてヘッドホンを直接繋いで使えない場合です。
オンボードのサウンド機能とか、安いサウンドカードなんかで良くある話ですねぇ。
以前のコラム記事で書いた様なアンプ内臓のスピーカシステムを使うのも良いと思います。
その他、HPアンプの能書きを見ると・・・再生機器から直接モニターしたい場合に、となってます。
ヘッドホン端子の付いていない機器につないで、ヘッドホンで聴く事が出来ますとも書いてます。
あんまり通常でこんな使い方をするとは思えませんねぇ。
良く聞く使い方としては、バンド活動とかしてる人がスタジオモニター用の補助としてです。
テンポや他の楽器の音とかをモニターしつつ演奏を行う場合に、「あともうちょっと音量が欲しい」ってコトがあります。
私もDTMをやってる時には、この音量不足で悩まされました。
そういう時に、ちょぃとこのHPアンプをかましてあげると解決なんですよねぇ。
もしくは音声ソースを途中でモニターしたい場合なんかにも都合が良いのです。
ちなみに、楽器演奏モニター用に使うんならば、ベリンガー製のHPアンプにその用途にぴったりなのがあります。
4本のヘッドホンが接続できて、それぞれにボリュームが付いてますからねぇ。
しかも機種によって端子がXLRだったり1/4TRSなどの、PA機器に準じたモノになってたりするのです。
もしも音楽鑑賞用としてのHPアンプをお求めならば、相応の機種を選ばなければなりません。
今回のようなクラスの製品は音量の確保が第一ですので、そこそこ良い音質では鳴りますがその程度です。
などと使い道を考えてると、意外と特殊なケースしか思い浮かばないんですよね。
なのでどちらかというと、特殊用途の機器ってコトになるんでしょう。
ポータブルオーディオ機器用のアンプとしては、電源の都合で持ち運びが出来ません。
据え置いて高級ヘッドホンで聴こうってのも判らなくないけれど、あんまり意味はないような。
私は以前、ヘッドホンを小型スピーカ代わりにするのにこのHPアンプ使ってました。
寝床にて夜中に使うので、音量が細かく調整できて何かと都合が良かったんです。
普通のスピーカから音を出すのは騒音問題になってしまうんで、耳元に近い所にヘッドホンを掛けておいて「手元スピーカ」とするんです。
いつもいつもDTMばかりやってるワケじゃないですから、有効利用しなければ。
|